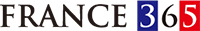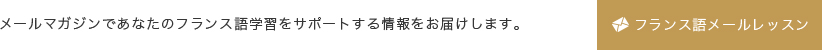2025年7月29日(火)、今週からフランスは本格的なバカンスシーズンになり、パリのメトロもラッシュアワーの混雑が緩和されてきました。世論調査によると、実はフランス国民の40%は「どこにも行っていない」一方、社会的な対面を保つためにバカンスに関してなにかしらのウソをつく人が多数いることもわかっています。
フランス人にとって「神聖」なバカンスも、所得で格差明白
社会の不平等観察を目的とする非営利団体、「オブザーバトワール・デ・イネガリテ」(Observatoire d’inégalités)が行った世論調査で、今年もフランス人全体の60%の人がバカンスに行くと答えています。しかしながら、収入別でみると、富裕層では76%、低所得層では42%と大きな格差があることが明らかになっています。
コロナ禍後初のバカンス予算減、借金も
また40%の人がインフレが夏のバカンス予算にも影響を与えている、と答え、30%の人はバカンスに行くために「ローン」を組んでいます。
ロックダウンが3か月続いた2020年、どこにも行けなかった反動で、2021年以降、インフレでもバカンス予算だけは維持していたフランス国民ですが、今年ついに一人当たりの予算が減少に転じています。
旅行比較サイトLiligoの発表によると、前年比で約73ユーロ(約12,600円/1ユーロ=約173円)減り、1,143ユーロ(約198,000円)になっています。
バカンスは「社会的ステイタス」を映し出す鏡
そして驚くことに、回答者の54%がバカンスに関して何かしら「ウソをついたことがある」ことが判明しています。
ウソの内容でもっと多いのは、バカンスの「期間」、「行先」、そしてバカンス中に「どんな体験をしたか」、といったものです。
旅行業界専門戦略コンサルタントのアーメル・ソレアック(Armelle Solelhac)氏は、「今に始まったことではない」この現象について、「フランス文化の重要な部分である旅行は、社会的ステイタスを映し出す鏡」であるからだと述べています。
ここ数年のインフレ、国際情勢やSNSの普及で一層エスカレートしています。
バカンス、つまり夏にとる長期休暇は、単に「休養のための時間」ではなく、「成功の証」、その人の「嗜好」、さらにはその人の「価値」を判断する材料になっているのです。
バカンス=その人の「アイデンティティ」
所属する社会的階級、個人的もしくは職業的交友関係によっては、自分の良いイメージを保つためにバカンスでの出来事を大げさに語る、といったことが重要になっています。
親が持っている「南仏のセカンドハウスで家族で過ごした」のか、「南仏に住んでいる実家に帰省した」のでは話が違ってきます。
さらには、「モルジブ島のリゾートで3週間過ごした」や「南アフリカでサファリ旅行」をしたり「日本に観光で3週間いった」のか、「フランス国内のセカンドハウスで過ごした」では、他人がその人に対してもつイメージが変わってきます。
「旅の土産話」=「パーソナル・ブランディング」
ソレアック氏は、バカンスは消費によって形成される一種のアイデンティティである、と指摘しています。つまり、我々は「何を消費し、どのように生き、何を共有するか」によって定義される社会に生きているのです。
他人を判断するのに、バッグや服、スマホや車などの「物質」はもちろんのこと、「旅行」も例外ではないということです。
旅行はいわば「パーソナル・ブランディング」に等しいと言えます。
旅行中の体験を実際より大げさに話したりして、「バカンスがいかに素晴らしかったか」を人に話すことは、聞いている人だけでなく、自分を納得させるためにも重要なことなのです。
一方、素晴らしいバカンスを過ごす予定だからこそ、周囲に一切話さない人もいます。バカンスによって自分を判断されるのを避けるためです。
SNSで「素晴らしいバカンス」への一層のプレッシャー
SNSの普及により、流行りの旅行先のチョイスに始まり、「インスタ映え」する宿泊施設、写真撮影時の「演出」やなどを気にする人が増えました。
バカンス中に「夢のようなストーリー(投稿)」をつくるために、自分もなにか人に語れる体験をしなければなければならない、そしてそれば「美しく」「独創的」で、「ちっと人がうらやましがる」ものでなくてはならない、という暗黙のプレッシャーが増しています。
そのため、バカンスを自宅で過ごした、キャンプにいった、というごく普通の休暇を過ごすのは格好悪い、恥ずかしいと、ウソをついたり話を美化したりするのです。
バカンスは「日本」とフランス人にいうと「うらやましい」と言われます。
在仏日本人にとっては単なる「帰省」で、日本に滞在中も決して楽しい事ばかりではないのが現実ですが、フランスでは「楽しかった」ことだけ話したほうがいいのかもしれませんね。
執筆:マダム・カトウ