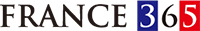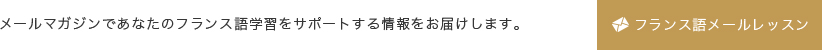ジュネーブの国連本部
私事ながら、国際会議や外交交渉の場に関わる機会がよくあります。国連などの国際的な会議場で最も多く用いられる言語は英語ですが、国連公用語であるフランス語での発言も認められています。そのためフランス人はもとより、他の国籍の人でフランス語で発言する参加者も多く見られます。
そういった国際会議でのフランス語を聞いていると、日常で話される標準フランス語とは少なからぬ隔たりがあることに気づきます。今回は私が国際会議において感じた、両者の際立った違いをいくつかご紹介してみたいと思います。

エッフェル塔のすぐそばにある国際機関UNESCOの本部
表現-芸術性より明確性
まず最も大きな違いは表現の仕方にあります。フランスの日常使用されるフランス語は、文化的で比喩的な表現を好む傾向が強くあります。政治家の演説や新聞記事、あるいは友人同士の会話でも、引用や皮肉・ユーモラスな言い回しが頻繁に登場します。
これは言葉そのものに芸術性や遊びを見出すフランス文化の一側面であるとともに、形容詞のみの表現よりも印象を残す効果もあると言えます。ただ文化的背景や考え方の基礎を共有していないと、予想外の誤解を招くリスクもあります。
国際会議ではそういったリスクが最も怖れられるため、芸術性ではなく誰もが同じ理解を得られる「明確性」を何よりも優先します。複雑なレトリックや曖昧な表現は、通訳にもフランス語を第二言語とする人にも、フランス語が母国語ながらフランス以外の文化圏から来ている人にも、理解の障害になりえます。
国際会議でよく耳にするフランス語は、短く論理的で誤解の余地を最小限に抑えたものが多いように思います。ある会合ではある代表が「C’est clair comme l’eau.(水のようにクリアだ)」という、フランス語では定番と言える比喩を使っていました。ですが議長が要約した際は単に「C’est évident.(明らかだ)」と置き換えていました。表現の芸術性よりも明確性を優先した例と言えるでしょう。

ジュネーブの国連の中にある国際会議場
発音-リエゾンは任意で
フランス語を学んだ人は一般に、喉を震わせる独特の“R”の発音や軽くドスの効いた鼻母音などをきちんと発音できることに憧れます。しかし国際会議の場でそういった細かい発音を重視する人は皆無。
理由は単純で、フランス語を話す人々の多くがフランス人ではないからです。フランス語話者はヨーロッパよりもアフリカに多く、カナダの一部やハイチなどにもいます。アラブ系やラテン系の方には巻き舌で“R”を発音する方もいますし、LとRを区別しない日本人には両方の発音が混ざっている方も多くいます。
特にアフリカ系の方のフランス語は語尾の母音をはっきりと発音する傾向があり、そのためリエゾンがないことも多々あります。そのため国際機関でのフランス語は、フランス国内の日常会話よりもはっきりと発音される印象で、日本人の私にはすらすらと流れるパリジャンのフランス語より分かりやすい気もします。
例えば「les enfants et les femmes(子どもと女性)」は、フランス式リエゾンをすると「レザンファンゼレファム」と一息に聞こえるはずです。ただ私がある国際会議で聞いた時は、「レ・アンファン・エ・レ・ファム」とすべてを切り離して発音していました。その発言者の発音の仕方なのかもしれませんが、標準フランス語を母国語とする人が少数派である国際会議の場では、こちらの方が「聞き手を配慮した発音」として誤解を生みにくいことは間違いないでしょう。
文法-細かい活用よりも伝わることが大事
フランス語を文法的に正しく話そうとすると、主語と動詞の一致や動詞の活用の使い分けなど、気にすべき点が多くあります。私を含めフランス語の学習をする人の最初の壁ではないでしょうか。しかし国際会議では、完璧な文法よりも「意味が伝わること」が優先されます。接続法などは無視して直説法を使ったり、時制が混ざっていたりすることも珍しくありません。重要なのは共通理解に到達することなので、伝われば細かいことは気にしないのです。
ある国の代表は「Il faut qu’on fait…」と、文法的には誤りである構文を繰り返し使っていました。しかし会議の進行に支障はなく、むしろ誰にでも伝わるフランス語として問題なく機能していました。フランス語教室なら「faitではなくfasseだよ」と訂正されるでしょうが、国際舞台では実用性を重視するのです。

パリ16区にある国際機関OECDの本部
違和感と安心感
初めて国際会議でフランス語を聞いたときは、どこか違和感を覚えました。学校で習ったフランス語やフランスで耳にした日常会話とはあまりに違い、なにか簡略化された別の言語のように聞こえたからです。リエゾンが必ずしも行われないことでテンポが不自然に感じられ、また文学的な比喩やユーモアの欠如には「そこがフランス語のいいところなのに…」とどこか物足りなさを感じたこともあります。
しかしスピードは抑えられ単語も明快で聞き間違えることが少ないように思え、安心感も得たのを覚えています。私のようにネイティブではない話者にとっては、パリジャンのフランス語よりも格段に分かりやすい気がしました。文化的背景が異なる人の間で使う「世界言語としてのフランス語」としては、パリのフランス語の洗練された響きよりも合理的と言ってもよいかもしれません。
こうして考えると、国際機関でのフランス語と標準フランス語は、目的の異なる「二つのフランス語」として共存していると言えます。前者は多様な国々の代表が意見を交わすための「ツール」であり、後者は文化的アイデンティティや美的感覚を映す「芸術的表現」である。この二つの言語は対立しているのではなく、むしろ補い合っているとも言えそうです。
執筆 Takashi