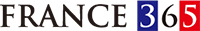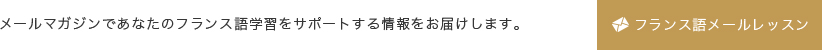2026年2月3日(火)、フランス全国どこへ行っても必ずあると思われたパン屋さん、その数は年々減少し、2024年には1,200件が閉業、その傾向は今年も続いてます。
2026年2月3日(火)、フランス全国どこへ行っても必ずあると思われたパン屋さん、その数は年々減少し、2024年には1,200件が閉業、その傾向は今年も続いてます。
フランスの村からパン屋が消える日
アルプ=マリティム県(Alpes-Maritimes)の小さな村、フォンタン(Fontan)にある唯一のパン屋さん、本来であれば閉業して年金生活に入る予定でしたが、その予定を半年先送りしました。店の設備や営業権を売却してまとまった資金を得て引退するはずでしたが、買い手となる後継者候補がみつかっていないのです。
このパン屋は、村に残されたわずか3軒の商店の一つで、常連客は「とてもおいしいパン屋さん。パン屋のない村は死んでいく」と語っています。
フランスにある人口数千人の村々では、すでに商店が次々と消えていく問題に直面しています。10年以上前には肉屋、八百屋(食料品店)、パン屋だけはこうした小さな町や村にも残っていましたが、まず肉屋が消え、パン屋の閉店も年々加速しています。
正直おいしくない?それでもスーパーで買う理由
フランスでは、パン(pain)というとバゲット(baguette)を指す事も少なくありません。
2022年にはユネスコの人類無形文化遺産に登録された「バゲット」は食事の際に食べる主食であり、日本でいう「ごはん」と同様の位置づけにあります。
そのため、毎日焼き立てのバゲットを買うのが長らく当たり前の習慣でした。
一方、クロワッサンやブリオシュなどバターの風味が強く甘味のあるパンは、朝食やおやつに食べるものと認識されています。
スーパーでもバゲットは買えますが、販売されているパンは工場生産のパンで、かつては品質が低く「おいしくないパン」の代名詞でした。(食品添加物が入っているものもあり)
パン屋さんのパンは「パリっと」した香ばしさが長持ちするのが特徴です。にもかかわらず、スーパーでパンを買う人が増えています。
スーパーに行く次いでにパンも買う、利便性
理由の一つは、村にスーパーがなく、車で近郊にある大型スーパーに買い物に行くため、ついでにそこでパンを買うというケースです。村にあるパン屋に行くにしても、徒歩圏内に住んでいない人は車で行かねばならず、利便性の面でスーパーに軍配があがります。
二つ目は、住んでいる村のパン屋が閉店してしまった場合や、パン屋が営業していない日曜日や祝日など、スーパー以外に買えるところがないというケースです。
パン屋が数多く存在するパリ市内でさえ、7月~8月のバカンスシーズンになると、パン屋が次々と閉まり、8月中旬ごろになるとスーパー以外ではほとんど購入できなくなります。
三つ目は経済的な理由です。
工場生産のパンは、一本ずつ手作りのパン屋のパンより当然安価で販売されています。
スーパーは価格で圧倒、価格重視の消費者
通常、地方のパン屋では1.15ユーロ(約210円/1ユーロ=約184円)前後で売られていますが、スーパーでは30サンチーム(約55円)~80サンチーム(約147円)とより安価で販売されています。需要の増加に目を付けた大手スーパーは、バゲットの販売を強化しており、中には「3本買うと4本目はタダ」、といった割引キャンペーンを行うところもあります。
インフレによる物価の高騰で、パンをスーパーで買う人は増え続けています。
サンドイッチも値上がり
一方、パン屋もランチ向けのサンドイッチやピザなど、高付加価値の商品を増やしていますが、特に数年前からは電気代や原材料価格の高騰で、ランチを「パン屋でサンドイッチを買って安く済ませる」選択も厳しくなってきています。
パリで販売されているバゲットパンのサンドイッチも、コロナ禍前は3~5ユーロ(約550円~約920円)でしたが、現在では5~7ユーロ(約920円~約1,290円)が一般的で、高いものは9ユーロ(約1,650円)の商品も販売されています。
フランス人の「パン離れ」が進む理由
1950年、フランス人が一日に消費するパンは325グラムでした。しかし現在では、その量は120グラムと半分以下にまで下がっています。
その理由の一つとして、まず朝食を食べない人が増えたり、朝食をシリアルにしてパンを食べない家庭が増えたりするなど、朝食文化の変化が挙げられます。
また、ここ10年ほどで、パン、特にバゲットに多く含まれる「グルテン」に対して、アレルギー反応を起こす人が増えてきました。
さらに、「ローカーブ(Low-Carb : 低炭水化物)」ダイエットの流行により、炭水化物の摂取を控える人が増え、キヌアなどの代替穀物の需要が増えています。
加えて、「一日にバゲット一本は食べられない、無駄になるから買わない」という人もいます。
ちなみに、たいていのパン屋さんでは「ドゥミ・バゲット」(demi‐baguette)と言うと、一本を半分に切って半額で売ってくれます。
執筆:マダム・カトウ