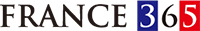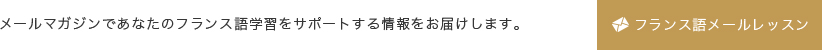フランスとイギリスは地理的にも文化的にも近く、良くも悪くもお互いに影響を与え合っています。
フランスとイギリスは地理的にも文化的にも近く、良くも悪くもお互いに影響を与え合っています。
エリザベス女王が亡くなった際は、王政を廃止して久しいフランスでもその功績を称える特別番組や王室の動向をこと細かに報じるニュースが放送され、注目度の高さがうかがえました。
そこで今回は、イギリスに関係するパリの場所をおもに文化の面から紹介するとともに、英仏関係についても簡単に考察してみたいと思います。
フランスにあるイギリス人の芸術作品
ルノワールやモネなどのフランス人画家とともに、印象派の時代を築いたアルフレッド・シスレー。
シスレーはパリで生まれ人生のほとんどをフランスで過ごしました。ただフランス国籍を取ることはなく、イギリス人として一生を終えたことはあまり知られていないかもしれません。
印象派の代表的な画家の一人として、彼の作品はオルセー美術館などに多く収蔵されています。
パリにはバンクシーの作品も
現代の有名なイギリス人芸術家といえば、匿名画家として知られるバンクシーがいます。彼の作品とされるものがパリにもありますが、消されたり盗まれたりしたものも多いようで、現存するのは19区の作品のみといわれています。
壁の落書きもひとつの芸術形態として市民権を得ているヨーロッパでは眉をひそめる人もおらず、時おり観光客が写真を撮ったりしています。
 ナポレオンの有名な肖像画をベースに政治的メッセージをこめたバンクシーらしい作品(筆者撮影)
ナポレオンの有名な肖像画をベースに政治的メッセージをこめたバンクシーらしい作品(筆者撮影)
パリで亡くなった英国人
パリ20区のペール=ラシェーズ墓地には、「幸福な王子」や「サロメ」の作者として有名なイギリス人作家のオスカー・ワイルドのお墓があります。
生涯放浪を続けていた彼はパリにも出たり入ったりという感じだったようですが、亡くなったのがパリ滞在中であったことからこの地に埋葬されたそうです。
ダイアナ妃のモニュメント
エリザベス女王の義娘であったダイアナ妃が亡くなったのがパリであることはよく知られています。
事故現場となったパリ16区のアルマ橋たもとのトンネルには、ダイアナ妃を追悼するモニュメントが建ち、没後25年が経つ今でも観光客がひっきりなしに写真を撮っています。
 アルマ橋たもとのダイアナ妃追悼モニュメント(筆者撮影)
アルマ橋たもとのダイアナ妃追悼モニュメント(筆者撮影)
モンマルトルのイギリス
パリ18区、モンマルトルの丘の北側斜面に Villa Léandre という Impasse(行き止まりの一画)があります。ここはイギリス人が Terrace house と呼ぶイギリス式の典型的な住宅が並び、他の地域とは違う雰囲気を醸し出しています。
パリでは珍しい一戸建て風で、どれもイギリス住宅の特徴である弓形の出窓と小さな前庭があります。ほとんどが1920年代に建てられたもので、当時流行していた英国・ノルマンディ風のスタイルを取り入れたのだそうです。
またここの10番地は、ロンドンのダウニング通り10番地にある首相官邸の門構えを模しているともいわれています。
この一帯はパリでは珍しい風景でもあり、雑誌や広告の撮影をしているところにもよく遭遇します。
ムーラン・ルージュにも
モンマルトルで最も有名なキャバレー、ムーラン・ルージュにもイギリスの影響が見られます。
ムーラン・ルージュの定番ダンスのフレンチ・カンカンは、もともとパリのキャバレーで流れていた音楽に、スカートの裾をめくって踊るイギリス発祥のダンスが合わさってできたそうです。
その証拠に「フレンチ」を付けるのは英語圏の人たちだけ。フランス人は単に「Cancan」と言い、「Cancan francais」とは誰も言いません。
 モンマルトルの Villa Léandre の街並み(筆者撮影)
モンマルトルの Villa Léandre の街並み(筆者撮影)
永遠のライバル?
韓国と日本、カナダとアメリカ…隣接する国が互いをライバル視するのはよくあること。中でもフランスとイギリスはその代表格と言えるのではないでしょうか。
中世には百年戦争で覇権を争い、その後も幾度となく戦火を交えた両国。20世紀の2回の大戦では味方として戦いましたが、その後はEU内で覇権を争い続け、シラク大統領とブレア首相が対立。ついには英国がEUを離脱と、仲が良いのか悪いのか分からない関係を何世紀も続けています。
人口規模や国力がよく似ていて距離的にも電車で行き来できるほどの近さだと、ライバル感が出てくるのは仕方ないのかもしれません。ですがやはりその近い距離感が、お互いの社会・文化に影響を与えているのも間違いないことです。
影響を与え合う関係
ロンドン発パリ行きのユーロスターでドーバー海峡を渡ると、車内アナウンスがフランス語に切り替わります。フランス語がまったくできない頃の私はそれがすごく優雅に聞こえて、感動したものです。
現在もパリの文化的密度の高さには飽きがきませんが、ビジネスも含めた世界への影響力では英語圏のロンドンには優っていないようにも感じます。
両国はお互いの良いところ悪いところを補完し合って、今後も発展していくことでしょう。
執筆:Takashi