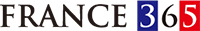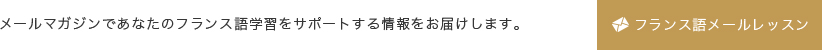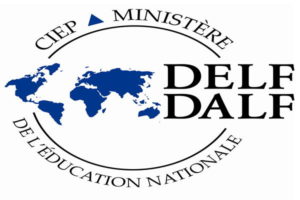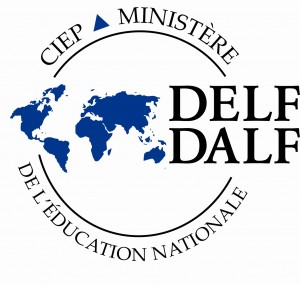
フランスの大学院進学に必須基準となる「DALF C1」(Diplôme approfondi de langue française)は、フランス政府認定の公式資格です。
C1の試験は、筆記試験と、面接試験からなります。
そして、筆記試験は、リスニング・読解・作文の3セクションに分かれています。以下では、それぞれの内容と対策のポイントをお伝えします。
(DALF C1の基本的な内容については、こちらの過去記事「DALF C1試験とは?その1」をご覧ください。)
リスニング(Compréhension de l’oral):約40分
リスニングは、インタビューや講演などの長文パートと、ラジオ番組やコマーシャルなどの短文パートの2つで構成されます。

長文パートと短文パートの特徴
長文パートは、8分程度の音声が流れ、配点は25点中の19点です。過去問題では「海岸の環境保護を行う活動家へのインタビュー」が材料となっているように、社会問題やアカデミック(学術的)な内容が含まれます。
初めに問題文を読む時間が数分あり、その後に音声が2回流れます。1回目と2回目の間には、回答のための時間が設けられています。
短文パートは、音声が数十秒ほどで、配点は25点中の6点です。題材はニュース番組や、コマーシャルなど、日常的なものが多いです。
このパートも、初めに問題文を読む時間が数十秒あり、その後に音声が流れます。一つの音声につき問題は1~3問と少なく、問題文も長文パートに比べてシンプルですが、音声は1回しか流れません。
リスニングは、設問形式に合った対策を
長文パートの設問は選択式、単語や数字の抜き書き、数行程度の記述式が組み合わせられており、それぞれの回答方式に慣れておく必要があります。
フランス語で、聞き取った内容を言い換えたり、理由などを簡潔にまとめたりする力も大切です。
短文パートは、選択式なのでシンプルそうに感じられるのですが、たった一回の音声で即座に内容を把握し、素早く正しい答えを選ぶには練習が必要です。
このように、C1のリスニング試験には長い文章をじっくり聞く前半と、短い文章を次々に聞く後半があります。それぞれの特徴を理解し、自分の得意な形式のものから対策しましょう。
読解(Compréhension des écrits):50分
読解は、文学作品や新聞記事などが出題され、A4で2ページほどの分量です。
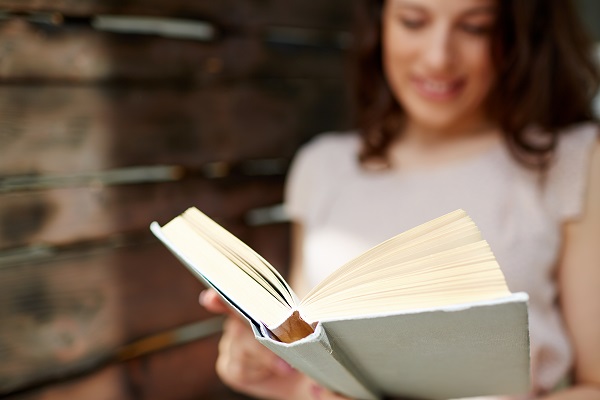
設問はさまざま、題材は文学的文章
2ページにわたる設問の中には、選択式や正誤選択、表の穴埋め、簡単な内容説明などが含まれています。
これらの問題は、文章中の一部分についての問題なのか、全体についての問題なのかが示されています。該当の箇所を参照しながら、答えられるようになっています。
過去問題ではモーパッサン(Maupassant/フランスの作家)の19世紀末の文章が材料になっており、筆者が実際に受験した時には、フーコー(Foucault/フランスの哲学者)の論説文が出されました。
読解は、文学的文章の攻略がカギ
文学的文章を読み解くのは、難しそうに感じられるかもしれません。しかし、フランス文学や近代思想について、時代背景など最低限の知識をつけるだけで、問題文がとても読みやすくなります。
例えば、過去問題では「詩的(poétique)な文学作品」と、「現実的(réaliste)な文学作品」の比較がテーマになっています。もし、“モーパッサンは「自然主義」の代表的な文学者である”ということが分かっていれば、論がどのように進められるか、予測がつきやすくなります。
文学や思想の知識は、新聞記事や論説文でも引用されることが多く、様々な形式の文章を読むのに役立ちます。
もちろん出題されるテーマは様々ですが、問題集や新聞などで出会った人物や出来事について、少しずつ調べて知識のストックを増やしていきましょう。
作文(Production écrite):150分
作文試験では、1000語程度のテキストが2~3本出題され、その要約(synthèse)と内容についてのエッセイ(essai argumenté)を書く力が問われます。

要約とエッセイの違い
解答する単語数は、要約が約220語、エッセイは約250語あり、A4サイズの解答用紙には横線のみが引かれています。150分の中で2問それぞれ構成を考え、下書きをして、ボールペンで清書します。
要約は複数のテキストの内容から、共通の部分を抽出し、重要な部分をまとめます。テキストの内容に忠実に、ただしコピーにならないよう単語の置き換えをしながら書きます。
エッセイはテキストの内容について、自分の考えや具体例を混ぜながら論じます。テキストの主張と、自分の主張の区別がはっきり分かるような構成が出来るかどうかが重要です。
出題テーマは、人文系と科学系の二種類
出題される文章のテーマは、受験を申し込む時に二つの中から選ぶことができます。一つは、「文芸・人文科学(Lettres et Sciences humaines)」、もう一つは「科学(Sciences)」です。
どちらにしても、「ル・モンドLe Monde」や「リベラシオンLibération」などの新聞記事や、インターネット記事が出典であり、読解の出題材料に比べると身近なテーマが多いです。
作文では、基礎と一貫性が大切
以上のようにC1は、要約やエッセイといった、高度な内容の文章作成力が問われる試験です。
採点基準のうち、両者に共通しているポイントは、基礎的な語学力と一貫性です。
まず、文法やつづりの正しさ、単語の使い方など、基本的なフランス語力が問われます。配点は小さいのですが、語数をしっかり守ることも大切。特に要約では、「220語」の指定であれば10%の増減(およそ200語以下、250語以上)を超えると減点されます。
そして、文章の一貫性とは、論の明確さや構成力のことです。
具体的には、要約では「選んだ情報を文章の形に構成し直す」力が、エッセイでは「構成やつなぎの言葉などを使用して、一貫性ある主張を行う」力が重視されています。
つまりエッセイの方では、接続詞や文章の並べ方など、文章の筋を通すための道具を使いこなせるように、対策すればよいということになります。
まとめ
リスニング・読解・作文の3セクションがあるC1の筆記試験について、お分かりいただけたでしょうか。
各セクションの中にも、様々な設問があります。この記事を参考に出題形式を研究して、対策に役立てていただけたら幸いです。
執筆あお