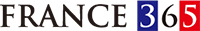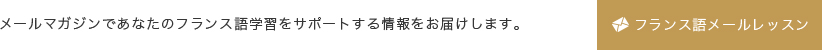10月7日(金)、ノーベル文学賞にフランスで初めて女性作家のアニー・エルノー(Annie Ernaux)氏が選ばれました。国内では1974年のデビュー以来、自伝的な作品で数々の文学賞を受賞した同氏ですが、今回の受賞により国際的な評価を動かぬものにしたとフランスのメディアは歓迎しています。フランスは世界で最もノーベル文学賞受賞者数が多く、1901年第一回目の受賞者シュリー・プリュードム(Sully Prudhomme)氏からエルノー氏を含め実に16人の受賞者を輩出しています。
10月7日(金)、ノーベル文学賞にフランスで初めて女性作家のアニー・エルノー(Annie Ernaux)氏が選ばれました。国内では1974年のデビュー以来、自伝的な作品で数々の文学賞を受賞した同氏ですが、今回の受賞により国際的な評価を動かぬものにしたとフランスのメディアは歓迎しています。フランスは世界で最もノーベル文学賞受賞者数が多く、1901年第一回目の受賞者シュリー・プリュードム(Sully Prudhomme)氏からエルノー氏を含め実に16人の受賞者を輩出しています。
自伝的作品、自らが生きた時代の女性像
今年82歳のエルノー氏は、ノルマンディー地方、セーヌ=マリティーム県(Seine-Maritime)のイヴト(Yvetot)という小さな町で食料雑貨店兼カフェを営む両親の娘として育ちました。
労働者階級であることを「恥じていた」聡明な彼女は、学問に励んで学校教師となり、さらにその後大学教授になりました。
アニー・エルノー氏がノーベル賞を受賞したことは、言い換えれば、階級の壁を超え社会的地位の向上を果たしたフランスにおける成功例が評価されたことでもあります。
自分の生まれ育った階級の人々を「裏切った」気持ち
文化教養に触れるとともに物質的な豊かさも手に入れたにもかかわらず、政治的には左派支持者であり続ける同氏は、同時に母や労働者階級の人々の中、つまり教養の乏しい環境に生まれ育った事にコンプレックスを持っていました。
出生を恥じると同時に、両親や自分が属していた階級の人々を裏切った気持ちを抱き、しかし彼らとは距離のある自分。エルノー氏は小説 「イヴトへの回帰」(仮題)(”Retour à Yvetot “)の中で、その葛藤にさらされた自分を「内面的(知性の)移民」と位置づけています。
自伝小説を書くことの「代償」
1984年にフランスではゴンクール賞(Prix Goncourt)と並んで権威ある文学賞、ルノドー賞(Renaudot)を受賞した『場所』(”La place”)、1988 年の『ある女』(“Une femme”)、97年の『恥』(”La honte”)といった作品には、アニー・エルノー氏の家族や親しい人たちにとっては時にゾッとするような内容が書かれていたりします。
「事実」を書くことには「代償」が伴います。
赤裸々な事実を明かすことは、作家本人にとっても決して心地良いことではありません。
エルノー氏は、自分の内面の深いところにある閉じ込められた怒り、静かにしかし絶え間なく続く決意を、飾りのない、平坦でユーモアも交えない「骨が見えるまで肉付けを剥ぎ取った」と言われるほどの赤裸々な文章で、素晴らしい芸術作品を作り上げています。
エルノー氏のノーベル文化賞の受賞理由について、アンデルス・オルソン(Anders Olsson)氏は、作家が「社会経験の中の矛盾、恥、蔑視、嫉妬、そして自分自身が誰だか見極めることが不能であることなどを、勇気を持って、かつ外科手術のような正確さで世に出し、その内容が時代を超えるものであること」だと述べています。
しかしながら、彼女の作品を称賛する声ばかりではありませんでした。
女性の解放と苦難
1940年生まれのエルノー氏は、同世代の女性たちが生きた飛翔と苦難の両方を描写します。
2000年の作品『事件』(”L’événement”)で、1963年に自らが経験した不法中絶で死にかけたことは自分の「解放」のために必要だったと表現し、『凍りついた女』(”La femme gelée”)では自身の離婚経験を、「写真の使い方」(仮題)(”L’usage de la photo”)では乳癌を患った経験を書いています。
女性解放を謳い、フェミニストでありながらも、1992年の『シンプルな情熱』(”Passion simple“)では、愛人男性との肉体関係にのめり込み、ついにその「男を待つことしかしなくなった」と告白しています。
「恥」、誰にも言えない「心の傷」
エルノー氏が後々までトラウマになった初めての性体験を書いたのは、作家デビュー後30年以上が経った2016年の作品「ある娘の記憶」(仮題)(”Mémoire de fille”)ですが、この作品でも「恥」を描写しています。
また最新作の短編「若い男」(仮題)(Le jeune homme)では、大人の女性と30歳年下の学生との叶わぬ恋を、そして2011年の作品『もう一人の娘』(仮題)(”L’autre fille”)では、両親との複雑な関係を描いています。
この作品では、子供の頃、自分が生まれる前に死んでしまった姉がいたことを知らされ、自分が常に姉の「代替えの子」であったことで傷ついていたこと、特に母親に「あの子は小さな聖人のようだった。今ここにいる子よりずっと優しい子だった」と言われたことでさらに傷が深まった体験が明らかにされています。
フランス文学界で「居場所がない気分」だった
権威あるルノドー賞をとった作家でありながら、フランスのメディアでアニー・エルノー氏が大きく騒がれることはありませんでした。
エルノー氏は1977年からパリ郊外のベッドタウン、セルジー=ポントワーズ(Cergy-Pontoise)に住み、特に彼女の2作品、『シンプルな情熱』と『事件』が最近映画化されたこともあり、「常に舞台の表に立って」精力的に活動を続けています。
フランスの文学界において、自分は「私生児」のようだと発言していた同氏ですが、ノーベル文化賞という最も権威ある賞を取ったことで、自分の居場所が見つかった気分になったのでしょうか。
エルノー氏は受賞後のインタビューで「世界に対して、正確かつ正義ある証言をし続ける」という「重大な責任」を負った気持ちだと答えています。
執筆:マダム・カトウ